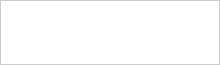六観音(ろくかんのん)とは、六道(りくどう)に迷い苦しむ衆生(しゅじょう:生きとし生けるもの)を救うために、観音菩薩がそれぞれ異なる姿に変化して現れたとされる六体の観音菩薩の総称です。
六道とは、仏教の世界観において、衆生がその生前の行い(業)によって生まれ変わるとされる6つの迷いの世界(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天道)のことです。観音菩薩は、その無限の慈悲によって、どの世界にいる衆生をも見捨てず、それぞれの苦しみに応じた姿で救済するという考え方が、六観音信仰の根底にあります。
六観音の組み合わせは、宗派や時代によって多少異なりますが、一般的には以下の6体と、それぞれが担当する六道が対応づけられています。
六観音の種類とそれぞれの役割・特徴
- 聖観音(しょうかんのん)
- 担当する六道: 地獄道(じごくどう)
- 特徴: 観音菩薩の基本的な姿であり、三十三観音の総元締めともいわれる最も古い観音様です。通常は一面二臂(いちめんにはん:顔が一つで腕が二本)で、何も持たないか、蓮の蕾や水瓶(すいびょう)などを持っていることが多いです。
- 役割: 地獄道に落ちた人々を救い、現世利益(げんぜりやく:この世でのご利益)全般を与えるとされます。地獄の苦しみから解放し、安楽の境地へと導きます。
- 千手観音(せんじゅかんのん)
- 担当する六道: 餓鬼道(がきどう)
- 特徴: 正式名称は「千手千眼観自在菩薩(せんじゅせんげんかんじざいぼさつ)」といいます。文字通り、千本の腕と千の眼を持つとされます。実際の像では42臂(腕)で表されることが多く、それぞれの手に様々な持物(じもつ:手に持つ道具)を持ち、千の眼で人々の苦しみを見つけ、千の腕で救いの手を差し伸べる姿を表しています。
- 役割: 餓鬼道に迷い、飢えや渇きに苦しむ人々を救済します。また、あらゆる災難、病気、苦しみから人々を救い、延命、病気平癒、夫婦円満、恋愛成就など、広大な功徳があるとされます。
- 馬頭観音(ばとうかんのん)
- 担当する六道: 畜生道(ちくしょうどう)
- 特徴: 観音様としては珍しく、**憤怒相(ふんぬそう:怒りの表情)**をしており、頭上に馬の頭を載せているのが特徴です。その怒りは、衆生の煩悩や悪を砕き、救済へと導くためのものです。
- 役割: 畜生道に迷い、本能や弱肉強食の世界で苦しむ動物や人々を救います。煩悩を食い尽くし、災難を取り除くとされ、家畜の守護、交通安全、厄除けなどのご利益があります。
- 十一面観音(じゅういちめんかんのん)
- 担当する六道: 修羅道(しゅらどう)
- 特徴: 頭の上に十一の顔を持つ観音様です。中央の慈悲相(じひそう)の他に、喜怒哀楽や笑いの表情など、様々な表情の顔を持ち、全方位を見守り、あらゆる人々の悩みや苦しみを救うとされます。
- 役割: 修羅道に迷い、争いや怒りに苦しむ人々を救います。また、病気、悩み、悪い心を取り除き、あらゆる願いを叶える功徳があるとされます。
- 如意輪観音(にょいりんかんのん)
- 担当する六道: 天道(てんどう)
- 特徴: 如意宝珠(にょいほうじゅ:意のままに願いを叶える宝珠)と法輪(ほうりん:煩悩を打ち砕き仏の教えを広める象徴)を持っている観音様です。片膝を立て、頬に手を当てる思惟(しゆい)のポーズを取ることが多く、人々をどうすれば救えるか深く考えている姿を表しています。多くは六臂像です。
- 役割: 天道に迷い、享楽に溺れ、やがて来る苦しみに気づかない人々を救います。智慧、財福、福徳を授け、安産、延命などのご利益があるとされます。
- 人間道を担当する観音 人間道を担当する観音については、宗派によって見解が分かれます。
- 准胝観音(じゅんでいかんのん)
- 宗派: 真言宗で多く採用されます。
- 特徴: 多くの腕(十八臂が多い)を持つ姿が特徴で、千手観音と似ていますが、胸の前で印を結んでいることが多いです。「准胝仏母(じゅんでいぶつも)」とも呼ばれ、無数の仏を生み出した母のような存在とされます。
- 役割: 人間道に迷い、様々な苦しみや煩悩を抱える人々を救います。特に清浄をもたらし、修道者を守護する功徳があるとされます。
- 不空羂索観音(ふくうけんじゃくかんのん)
- 宗派: 天台宗で多く採用されます。
- 特徴: 手に羂索(けんじゃく:投げ縄のようなもの)を持つのが特徴です。この羂索は、すべての衆生をもらさず救い取るという観音様の慈悲を表しています。一面三眼(顔が一つで眼が三つ)の像もあります。
- 役割: 人間道に迷い、様々な苦しみや煩悩を抱える人々を、決して漏らさずに救い取るとされます。災難除去や延命のご利益があります。
- 准胝観音(じゅんでいかんのん)
六観音信仰の広がり
六観音信仰は、平安時代中期ごろから広がり始め、特に六道輪廻の思想が人々に深く浸透する中で発展しました。各地に六観音を祀る寺院が建立され、人々は六道それぞれの苦しみから救われることを願って信仰しました。
現代でも、六観音を祀る寺院は多く存在し、人々の心の拠り所となっています。それぞれの観音様が担う役割を知ることで、私たちが日々の生活で感じる様々な悩みや困難に対して、より深く仏様の慈悲を感じ、心の平穏を得る助けとなるでしょう。