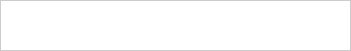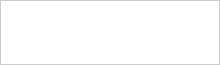あなたも僧侶になりませんか?
愛知県で僧侶になりたい!お坊さんになりたい!そんな気持ちの方を
真和会真和寺では全力でサポートします。
仏教の教えを深く学び、修行を積み、僧侶としての活躍していただくため、
まずは得度を受けて頂きます。
得度(とくど)は、仏教において、在家者(一般の人)が仏門に入り、仏の弟子として出家し、僧侶となるための儀式を指します。文字通りには「度(わた)ることを得る」という意味で、迷いや苦しみの世界(此岸)から悟りの世界(彼岸)へと渡る第一歩を踏み出すことを象徴しています。
これは単なる資格取得ではなく、生き方そのものを仏道に捧げるという、人生における非常に大きな決断と転換点となります。
得度式はあくまでスタートラインであり、その後が本当の修行の始まりです。
得度の種類
得度には、大きく分けて二つの種類があります。
- 出家得度(しゅっけとくど):
- 僧侶になるための得度で、一般的に「お坊さんになる」と言う場合はこちらを指します。
- 得度後は、僧衣をまとい、剃髪(ていはつ:髪を剃る)し、寺院で修行生活を送りながら、仏道を学び、実践し、人々に教えを伝える役割を担います。
- 多くの場合、得度後にさらに専門的な修行や学問(宗派の大学や専門道場での学びなど)が必要とされ、それらを修了して初めて、法事や葬儀を執り行ったり、寺院の住職になったりするための教師資格(僧侶としての正式な資格)が与えられます。
- 在家得度(ざいけとくど):
- 出家せず、一般社会人として生活しながら仏教を深く学び、戒律を守って仏道を歩むことを目的とした得度です。「プチ出家」などと呼ばれることもあります。
- 剃髪はしない場合が多く、家庭を持ち、仕事も続けながら、日々の生活の中で仏教の教えを実践します。
- 得度式で戒名(法名)や在家用の袈裟(輪袈裟など)を授けられます。僧侶のように公の場で法要を執り行うことは通常できませんが、信仰を深めるための重要な節目となります。
- 一部の宗派では、在家得度を経てから出家得度に進む道も開かれています。
1. 入門
- 僧侶を目指す者は、まず真和会に入門します。ここでは師僧(師匠となる僧侶)、その僧侶の指導のもとで修行を開始します。
2. 戒律の学習
- 僧侶として守るべき戒律(戒律や道徳的な規範)を学びます。戒律は宗派や地域によって異なりますが、基本的には「殺生しない」「盗まない」「嘘をつかない」「酒を飲まない」などが含まれます。
3. 経典(お経)の学習
- 仏教の教えを記した経典(お経)を学びます。これには、仏教の根本的な教義や哲学、歴史などが含まれます。お経の理解は、法話等において重要です。
4. 修行
- 日々の修行として、声明(お経の唱え方)、念仏、写経などを行います。 これらの修行は、心を静め、仏教の教えを実生活で実践するための精神的な基盤を築くものです。
- オンラインでの修行に対応致します。お時間を合わせてオンラインでの修行も可能です。
5. 実践と奉仕
- 修行が進むと、僧侶としての作法や所作を習得し僧侶としての実務も行うようになります。これには、法要や葬儀の執行、地域社会への奉仕活動などが含まれます。
6. 僧位の取得
- 一定の修行期間や学習を経て、僧位(僧侶としての資格や地位)を取得します。これにより正式な僧侶として活動することができるようになります。
7. 生涯修行
- 僧侶の道は一生涯続く修行の道です。僧侶となった後も、常に学びと修行を続け、仏教の教えを深め、人々を導く役割を果たし続けます。
これらの過程を経て、僧侶は仏教の教えを体現し、社会に貢献する存在となります。
8.得度冥加料:30万円(基本的にこれ以上はかかりません)
僧衣法具等は別途ご購入して頂きますがサポートさせていただきます。(概ね最初は5万円くらい~)
得度に関する質問
質問:僧侶になるのに年齢制限はありますか?
回答:年齢、性別に制限はありません。
質問:得度をした後の修行は厳しいものですか?
回答:お釈迦様は厳しい修行を数年されましたが、悟りを開くことができませんでした。
真和会真和寺においても厳しい修行はありません。ただ、作法やお経の読み方等はご指導させて頂きます。
質問:得度したら法要や葬儀には行けますか?
回答:得度後に作法やお経の読み方(声明しょうみょう)を学んでいただき、
代表ができると判断したらまずは法事から行って頂きます。
葬儀(引導)の作法は一番最後にお教えいたします。
質問:得度の際に頭は剃らなければいけませんか?
回答:真和会真和寺では必ずしも剃髪の必要はありません。
質問:今の仕事をしながら僧侶もできますか(兼業僧侶)
回答:もちろんできます。
質問:愛知県在住ではないのですが、得度できますか?
回答:もちろんできます。お気軽にご相談ください。
質問:僧侶にならず、先祖供養のため得度したいのですが可能ですか?
回答:可能です。非常に稀有な機会となりますのでご検討ください。
得度(とくど)は、仏教において、在家者(一般の人)が仏門に入り、仏の弟子として出家し、僧侶となるための儀式を指します。文字通りには「度(わた)ることを得る」という意味で、迷いや苦しみの世界(此岸)から悟りの世界(彼岸)へと渡る第一歩を踏み出すことを象徴しています。
これは単なる資格取得ではなく、生き方そのものを仏道に捧げるという、人生における非常に大きな決断と転換点となります。
得度の一般的な流れ(出家得度の場合)
宗派や寺院によって詳細な流れは異なりますが、一般的には以下のステップを経ます。
- 師となる僧侶を見つける:
- 最も重要なステップです。自分が帰依したい宗派の寺院を訪ね、師(お師僧様)となる僧侶に直接相談し、弟子入りを志願します。この師弟関係は、その後の修行や僧侶としての人生において非常に重要になります。
- 入門・準備期間:
- すぐに得度式が行われるわけではありません。師僧のもとで一定期間、仏教の基礎知識や寺院での作法を学び、僧侶になる覚悟と適性があるかを見極める期間となります。
- この期間に、得度に必要な装束(白衣、袈裟など)や数珠などの仏具を準備します。
- 得度式(儀式):
- 師僧の立ち会いのもと、寺院の本堂などで執り行われる正式な儀式です。
- 剃髪: 世俗との決別を意味し、頭髪を剃り落とします(宗派によっては、部分的な剃髪や、この時のみ有髪が認められる場合もありますが、一般的には行われます)。
- 受戒(じゅかい): 僧侶として守るべき戒律(仏の教えを実践するための行動規範)を授けられます。戒律の種類や数は宗派によって異なります(例:五戒、十重禁戒など)。
- 法名(ほうみょう)の授与: 仏弟子としての新たな名前が師僧から与えられます。
- 衣の着用: 僧侶の象徴である墨染めの衣(袈裟など)を身につけます。
- これらを通して、正式に仏弟子となり、僧侶への道が始まります。
- その後の修行・学問:
- 得度式はあくまでスタートラインであり、その後が本当の修行の始まりです。
- 専門道場での修行: 多くの宗派では、得度後に数週間から数年間の専門道場(僧堂、修行道場など)での厳しい修行が課せられます。ここでは、坐禅、読経、作務(清掃や労働)、托鉢(宗派による)など、集団生活の中で仏道の精神と実践を徹底的に学びます。
- 宗門大学での学業: 仏教の教義、歴史、哲学などを体系的に学ぶために、宗門系の大学に進学する場合もあります(例:駒澤大学、龍谷大学、高野山大学など)。
- これらの修行や学業を修了して、ようやく教師資格を取得し、布教活動や寺院運営などの僧侶としての本格的な活動ができるようになります。
得度に必要な費用と期間
費用や期間は、宗派、寺院、受ける得度の種類(出家得度か在家得度か)によって大きく異なります。
- 費用:
- 入度料・冥加金: 宗派や寺院に納める費用です。数万円から数十万円、場合によってはそれ以上かかることもあります。
- 修行費用: 専門道場での修行期間中の滞在費や、講習費などが発生します。
- 法衣・仏具: 袈裟、数珠、白衣などの購入費用。これらは数万円から数十万円かかることがあります。
- その他、交通費や準備費用など。
- 期間:
- 在家得度: 短期間(数日~数週間)の講習や儀式のみの場合が多いです。
- 出家得度: 得度式自体は1日や数日ですが、その後の修行期間が数週間~数年に及ぶことが一般的です。宗門大学での学業を含めると、さらに長期間になります。
僧侶になることの覚悟と心構え
得度は、単に「お坊さん」という肩書を得るだけではありません。
- 仏教への深い信仰: 仏の教えを信じ、その道を歩む強い意思が必要です。
- 世俗的な価値観からの転換: 物質的な豊かさや地位よりも、精神的な充足や人々の救済を優先する心構えが求められます。
- 戒律の遵守: 僧侶として守るべき戒律があり、それに従って生活する規律が必要です。
- 学び続ける姿勢: 仏教の教えは奥深く、生涯にわたって学び、実践し続ける努力が求められます。
- 利他行の実践: 自己の悟りだけでなく、他者の苦しみを救うための行動(利他行)を実践する精神が重要です。